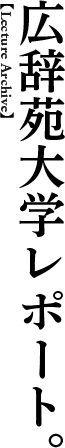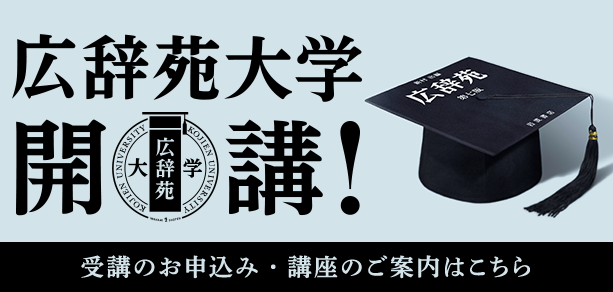言葉の意味や重さはどんどん変化していく。日本を動かしたほどの影響力の大きな言葉でさえ、時代とともに盛衰があり、浮き沈みがある。
広辞苑をテキストに、さまざまなフィールドで活躍するプロフェッショナルに多様な切り口の「言葉」にまつわるお話をいただく広辞苑大学。この講座では、東京大学名誉教授の三谷太一郎氏とともに、近代日本を動かした言葉「富国強兵」と「文明開化」という二つの言葉の変遷を追った。
何のために勉強するのか。文明開化のモチベーション
広辞苑で、近代を引くと、こんなふうに書かれている。
近代【きんだい】歴史の時代区分の一つで、日本史では明治維新から太平洋戦争の終結までとするのが通説。
一応この見解を前提とすると、この間の近代の日本で、合い言葉のように使われていたのが、「文明開化」と「富国強兵」の二つの言葉だ。
ここで、その二つの言葉も広辞苑で引いてみると、それぞれ、こう書かれている。
富国強兵【ふこくきょうへい】国を富ませ、兵力を強めること。富強。
中学や高校の歴史の授業で習ったことと、そう変わりはないのではないだろうか。
広辞苑では、この言葉の解説に加えて、「富国強兵」の項目に、福沢諭吉の『世界国尽(せかいくにづくし)』という本が出典としてあげられている。
「人民恒の産を得て富国強兵天下一、文明開化の中心と名のみにあらず」

この『世界国尽』というのは、福沢諭吉が19世紀半ばの世界の国々の特徴について説明した教科書的な解説だ。幕末に幕府から派遣されて主として欧米諸国を訪れた福沢が、世界は大きく5つの地域(洲)に分かれていて、それぞれの国の広さや文化はこんな感じなんだよと、平易な文章で解説している。
(福沢は浄土真宗の蓮如の文章に影響を受けて、読者に分かりやすく読みやすい文章を心がけていたらしい)
その『世界国尽』で福沢は言う。
世界には色んな国があって、未開の地もあるし、アメリカやイギリスみたいに文明開化に至っている国もある。商売も繁盛し、武力も充分で、芸術も盛んな、進んだ国というのは、実は、そのベースとなる学問をしっかりやっている。文明が花開いた、そのキラキラした花の部分だけを見て真似してもダメで、文明開化のためには、ちゃんとその根っこにある学問からやらないといけないと説いているのだ。
ちょっと長くなるが、ここにヨーロッパについて書いている原文(表記は現代的に書き換えた部分もある)を載せておこう。(七五調で朗読向きの文なので、口に出して読んでみるのもいい)
狭き国土に空き地なく、人民恒の産を得て富国強兵天下一、文明開化の中心と名のみにあらず、その実は人の教えの行き届き、徳義を修め、知を開き、文学・技芸・美を尽くし、都(みやこ)鄙(いなか)の差別なく、諸方に建つる学問所、幾千万の数知らず。彼の産業の安くして、彼の商売の繁盛し、兵備整い、武器足りて、世界に誇る太平の、その源を尋ぬるに、本を務むる学問の枝に先たる花ならん。花見て花を羨むな。本なき枝に花はなし。一身(ひとみ)の学に急ぐこそ、進歩(あゆみ)はかどる回り道。共に辿りて、西洋の道に栄ゆる花を見ん。
世界のなかでも後発だった日本が、欧米に負けない軍事力をつけ、国を富ませるためには、洋学を勉強しないと。そんな考えがあったから、後に、『学問のススメ』を書くに至ったのだろう。
『学問のススメ』は当時、庶民にも広く読まれた。国を発展させるために、外国の学問も勉強しないといけないんだと、洋学をやる目的を明確に打ち出したのは、彼の本が初めてだったからだ。混乱の世で、洋学というのは、当時の最先進国だったヨーロッパ諸国に追いつけ追い越せのために必要なことなんだとハッキリと示した、福沢の主張は庶民の心をも動かした。
発想のタネは幕末から既に生まれていた
ちなみに、「文明開化」や「富国強兵」という言葉は、明治の世になって、突然、生まれてきたものではない。その前にちゃんと伏線があった。富国強兵というのは、実は、幕末の混乱のなかで、幕府側が打ち出した体制の近代化路線のスローガンだったのだ。
同じく、福沢諭吉が書いたものに、その片鱗が見えるから、いくつか例をひいてみよう。
福沢諭吉は、幕末に翻訳方という外交の実務の末端に従事していた幕臣で、1862年には幕府の視察団についてヨーロッパを訪れている。そして、滞在先のロンドンから地元の中津藩の藩士に向けて、こんな手紙を送っていた。
「今、急がなければいけないのは富国強兵だろう。そのためには人材育成が重要だ。これまでお屋敷で人を引き立てる時には漢書が読めることを重視してきたけれど、漢書も読みようによっては実務の役には立たない。人材を育成するのに必ず漢書でなければいけないということもないだろう」
漢学ではなく洋学の教育が必要だと、彼はこの時代から強調していたのだ。
そして、その数年後には、別の手紙で、日本の政治体制について述べている。
「従来の幕藩体制では、あちこちの藩がただ国内で足の引っ張り合いをするだけで、ちっとも文明開化が進まない。今のご時世で大名同盟を支持するということは、一国の文明開化を遅らせることで、世界的に見たら罪深いことだ」。
日本の国を発展させて、文明開化のステージに至らせるには、全国あちこちに支配者が乱立していたのではダメで、独裁者による統治(大君のモナルキ)が必要だと考えていたようだ。
特に、1866年に反幕府的な動きをしていた長州藩を幕府が制圧しようとしていた時には、「長州再征に関する建白書」という意見書を書いていて、そのなかでも将来の政治体制について言及している。
「長州を倒せば、その分の歳入が増えるだろう。それを担保とすれば、幕府と近しいフランスに借金できるはずだ。そのお金で外国人を雇って軍備を増強すればいい。そうして長州をとりつぶした上で、異論を唱える大名や京都の朝廷にも圧力をかけ、これを機に日本の封建制度を一挙に変革してしまってもいいぐらいだ」と。
福沢は当時海外をあちこち見てきていたから、近代化の遅れに対する危機感も強かった。日本の社会の仕組みそのものを変えないと近代化できないと考えていた。このように明治維新の前から既に、福沢らの先進的知識人を通じて、「文明開化」「富国強兵」のスローガンが生まれる土壌はできていたのだ。
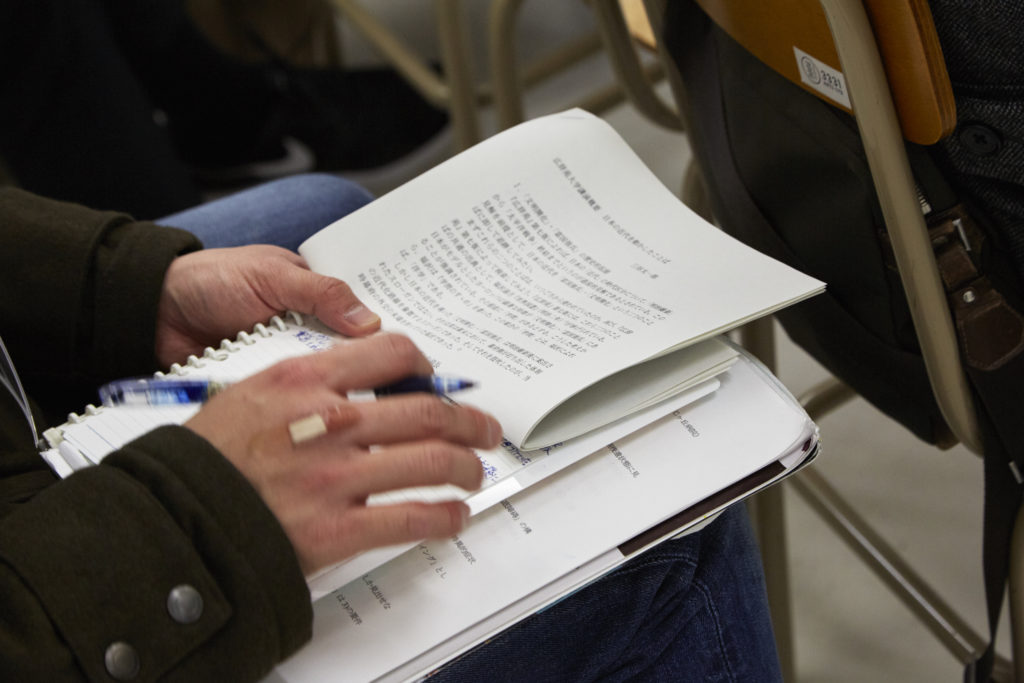
「強兵」が求められない時期もあった
明治の時代に入ると、日本は欧米に倣って、急速に近代国家へと国の体裁を変えようとした。新政府による中央集権制ができ、積極的な殖産興業を推し進めて、「文明開化」「富国強兵」は徐々に現実のものとなり、海外列強と比肩するようになっていった。
ところが、大正時代に入ると、この2つのスローガンの影響力が低下する。とりわけ、「富国強兵」はさほど重視されなくなった。第一次世界大戦後世界情勢が変わったからだ。
この時期、世界ではイギリスが国際的な覇権を失って、国際政治の多極化が進み、複数の有力国が世界の動向を形づくる新しい国際政治体制へと移っていく。後の冷戦期の米ソの覇権体制が作られる過渡期だった。一国が軍事力、経済力で世界ににらみをきかせることが難しくなったのだ。
第一次世界大戦では、複数の国が同盟を結んで戦ったし、第一次世界大戦後には戦争の再発防止に向けて、国際連盟がつくられた。さらに、東アジアについてはワシントン会議が開かれて、海軍軍縮も進んだ。
(ちなみに、英語が国際会議の公用語になったのは、このワシントン会議の時が初めてだった。そのことは、第一次世界大戦後の米国の国際的地位の飛躍的向上を反映していた。それまでは英語はフランス語に比べて、国際語としては認知度が低かったのだ。)
一連の国際会議等の国際的コミュニケーションを通じて、この時代には第一次世界大戦前のヨーロッパの枠を超えた「世界」という概念が生まれ、「国際社会」という新しい概念もつくられたのだ。
長谷川如是閑という大正デモクラシー期のジャーナリストは、これを評して、国際関係がinter-state(国家間)もしくはinter-nation(民族間)の関係から、inter-social(市民社会間)の関係に変わりつつあると指摘している。
国際政治学という学問ができたのもこの頃の話だ。蝋山政道という政治学者は、これまでの国家政治学では捉えきれない、国際社会というものを対象とする新しい学問分野が必要だと、当時著した書物(『政治学の任務と対象』1925年)のなかで言っている。
そんなふうに、世界の国々が経済を中心として国際的な協力体制を築こうとする、新しい潮流があるなかで、一国が突出して軍事力や経済力で国際的な支配体制を確立しようとするのは困難だ。
また、第一次世界大戦で帝政ドイツや帝政ロシアのような軍事大国が、対外的な戦争それ自体よりも、国内の革命によって内側から崩壊し、国際的に軍事力に対する信仰が失墜した。そこで、各国において、「富国」はともかく、「強兵」へのモチベーションは衰えた。
第二次大戦前、世の中はどんな空気だったのか?
一度は下火になった「富国強兵」のスローガンがまた、新しい意匠をまとって急浮上してくるのが、第二次世界大戦の直前の頃だ。第一次世界大戦の「戦後」から、第二次世界大戦の「戦前」への転換が始まるころからだ。
世界の国々は国際連盟の下で、軍縮による国際協調体制(ヨーロッパにおけるヴェルサイユ体制、東アジアにおけるワシントン体制)をつくったが、ヨーロッパにおいてはナチス・ドイツやファシスト・イタリー、東アジアにおいては反政党政治、軍国主義化の傾向を深める日本によって、第一次世界大戦後の戦後体制は破綻の兆候を見せ始める。ここで再び、「強兵」にアクセントを置いた「富国強兵」のスローガンが台頭してくる。
満州事変以後、軍部を急先鋒とする日本は、高度国防国家のモデルとして満州国をつくり、その制度や機構を日本本国に逆輸入した。議会でものごとを決める仕組みを変え、政党はすべて解散し、満州国の協和会に倣った大政翼賛会の傘下に入れ、日本中を一気にコントロールできる仕組みをつくろうとした。戦争のための国づくりだ。国家機構が「強兵」を意識したものになった。
この時期の朝日新聞には、「強兵」のための人口政策として「産めよ増やせよ」を推奨する厚生省の当局者の談話が掲載されている。当時、厚生省に人口問題を担当する部局ができ、それを担当する役職についた古屋芳雄という技官が、フランスがナチス・ドイツに負けた原因の一つは出生率の低さだと語っている。今日でいう「少子化」の指摘である。しかもそれを特定のイデオロギーに帰した。「個人主義、自由主義が進むと、出生率が落ちるので、そんな思想は早く放棄して人口を増やす国策に協力せよ」などと述べたと記事にはある。日本において「少子化」への危機感が生ずるのは、フランスの作家アンドレ・モーロアの『フランス敗れたり』という著書の翻訳がベストセラーとなった時期であり、「強兵」への切迫感が「少子化」への危機感を駆り立てた。
広辞苑によると、「少子化」という言葉が使われたのは、1992年度の『国民生活白書』だということであるが、その起源は、遡って、第二次世界大戦におけるナチス・ドイツに対するフランスの敗戦にあったといえよう。
また詳細は省くが、当時の日本は、国よりも、もっと広く大きく、アジア圏(後の「(大)東亜共栄圏」を志向するようになっていった。「国」よりも、「圏」という広い地域を重視する「地域主義」的発想だ。これに合わせて、今日でも時々言及される「地政学」が流行した。
言葉の意味は時代によって変わる
第二次世界大戦が終わり、憲法第九条がつくられと、「強兵」は、完全に日本の政治を動かす言葉ではなくなった。戦後の復興期には、日本は「強兵」から切り離された「富国」に邁進することになる。その際、敗戦日本は再出発に当って、どこに立ち戻るべきなのかという議論が行われ、結論として日清戦争前の明治日本、つまり、「富国強兵」前の日本を再出発点とすべきだということが言われたという。
以上、「文明開化」・「富国強兵」という二つの言葉の消長を通して、幕末から太平洋戦争の敗戦までの日本の近代を一応概観した。日本の社会の状況と日本を取り巻く世界の状況とによって、「文明開化」・「富国強兵」という二つの言葉のそれぞれの意味や評価、さらに相互関係が変わってきたことは理解できたかと思う。
「広辞苑を引くバカ広辞苑を引かぬバカ」という言葉があるそうだ。
広辞苑はたくさんの言葉が収録され、“知識の入り口”だと言われている。辞書を引けばすぐに分かるのに、引かないままでいるのは引かぬバカである。
一方で、広辞苑が世の中のすべてを説明しているわけではなく、辞書に書かれた内容を鵜呑みにするのもナンセンスなことで、これは辞書を引くバカである。
広辞苑で、二つの言葉の意味を引くところから始まった講座。日本を動かしたほどの言葉も、時代によってずいぶん意味合いや比重が変化してきたという結論は、辞書を引くバカになってはいけないということを改めて教えてくれているようだ。

全編動画レポートもお楽しみください。